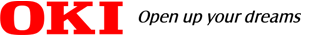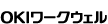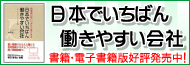- Home
- 職場がおうちへやってきた
- 第12回 - OKIワークウェル創業
職場がおうちへやってきた
職場がおうちへやってきた 第12回 - OKIワークウェル創業
[2009年10月8日掲載]
ワークウェルコミュニケータの開発
複数の在宅勤務者がチームとなり、本社オフィスにいるコーディネーターの管理のもとで、ディレクター(リーダー的な在宅勤務者)を中心とした共同作業を行う。これがOKIワークウェルの業務システムの基本である。
このような形態において重要になるのは、関係者間のコミュニケーションである。基本的には電子メールを使って行うが、思い違いなどを防ぐために、電話も盛んに利用することになる。
しかし、一対一のやりとりだけでは効率が悪い。一斉指示など、チーム全体への連絡が困難だからである。また、共同作業においては、それぞれの専門技術を背景にしたチーム・ミーティングが必要となる場合も多い。関係者全員がリアルタイムに反応し合えなければ、時間と労力ばかりがかかってしまう。
そもそも、在宅勤務には孤独感が生じやすいという問題がある。各プロジェクトはチームワークによって進められてはいるが、作業そのものは単独行動である。自己管理が要求され、感情としては張りつめた状態が続く。順調な時は良い。しかし、作業が捗らないと、自分だけが出遅れているような焦りを感じる。上長に指導や忠告を受ければ、それをたった一人で受け止めなければならない。まさに孤独との闘いである。
このような、在宅勤務ならではのマイナス要素をサポートするには、どうすればよいのか。OKIワークウェルにとっても通らざるを得ない、最大の難問であった。
「多地点の常時接続型音声会議システムを導入してはいかがでしょう」
新たな課題に立ち向かう木村や津田に、そんな助言をくれた人物がいる。OKI研究開発本部ヒューマンインタフェースラボラトリ(当時)の竹内晃一氏である。
竹内氏はOKIにおいて、IT分野の障害者アクセシビリティなどを専門に研究していた。スタンフォード大学で、訪問研究員としてトータル・アクセス・システム(さまざまな代替入出力機器の共通インターフェース)の開発に従事。また社会人学生として、東京大学の先端科学技術研究センター博士課程で学ぶなど、その熱心な研究ぶりには内外で定評がある。OKIネットワーカーズに対しては、発足当時からアドバイザー的に関わってきた。
津田はこう語る。
「OKIワークウェル設立の頃から、竹内さんとは、在宅勤務に適したシステムについてよく議論していました。OKIネットワーカーズの人数が増えてきたので、コミュニケーション効率の上がるツールがあるといいのだが、という相談をしたんです」
竹内氏はその後、さまざまな場面でOKIワークウェルと行動を共にする。そのうちの一つは、カナダのトロント大学と共同で行った“ボーカル・ビレッジ(Vocal Village)”の実証実験であった。
トロント大学で開発されたボーカル・ビレッジは、VoIP(TCP/IPネットワークを使った音声データの送受信技術)を用いた、多地点対応の音声会議システムである。常時接続しておけば、いつでも複数人での音声会議ができるというものだ。
こうした音声会議システムが、在宅勤務の現場にどのような効果をもたらすのか。それを実際のウェブ開発業務において確かめるべく、OKIワークウェルでボーカル・ビレッジの導入実験を試みたのである。
実験には約2週間を費やし、OKIネットワーカーズから7名が参加した。作業時間中、参加メンバーはボーカル・ビレッジに常時接続しながら、いつものように業務を行った。
実験後にとったアンケートでは、多くのメンバーが、チーム内でのコミュニケーションが改善されたと回答している。「仲間と一緒に仕事をしている」とか「自分の意見が反映されている」といった意識が向上した、というのである。
しかも電話に比べ、通信費の大幅な削減が期待できる。
多地点音声会議システムが、テレワークの在宅勤務を支援するものとして有用なものであることが分かった。このような音声会議システムを、OKIワークウェルで本格的に取り入れたい。津田は強くそう思った。
しかしボーカル・ビレッジは、さまざまな理由から、OKIワークウェルの在宅勤務におけるベースのシステムにはならないという判断になった。
「この際、独自の多地点音声会議システムを開発しましょう」
そんな提案が、竹内氏から出された。OKIには音声通信技術があり、それを応用すれば何とかなるのではないか、というのだ。
実は社長の木村も、ひそかにそれを考えていた。実現すれば、会社の業務ツールのみならず、様々なテレワーカの支援にも役立つものになるだろう。しかも、新しいビジネスになるかもしれない。そんなふうに思っていたのである。
木村は腕を組み、チェアに深く背をもたれた。
「ただ……。費用をどうするかだ」
ベンチャーで始めた小さな会社である。一つのものに、大きな資金を注ぎ込むような余裕はない。
すると、竹内氏が一つのアイディアをくれた。
「情報通信研究機構っていうのがありますよね」
情報通信研究機構(NICT)。情報通信に関する研究開発や事業の支援を行っている、総務省所管の独立行政法人である。
「高齢者と障害者向けのシステムの研究開発のために、助成金の募集をしているんです。障害者が使いやすいコミュニケーションツールの研究開発、ということで応募してみませんか」
「竹内さん、それがいい!」
木村と津田は早速、竹内氏に相談に乗ってもらいながら、目指すべく多地点音声会議システムの開発方針をまとめた。
- 重度障害者でも使いやすい、ユーザーインターフェース
- 大学の福祉機器研究者などにも研究委託する。
- 社内の在宅勤務障害者が実際の業務で実験使用する。
- 長時間使用しても、ストレスのないクリアな音質で遅延がないこと
- 音質確保に注力するため、映像機能は省く。
- ユーザー提供価格を安価にすること
- 可能な限りオープンソースを活用する。
- 映像機能は優先度が低いので、開発項目から省く。
このアイディアでNICTへの助成金の申請をし、それが認められた。さらに、OKI関連の技術協力も得られることになった。こうした動きが、短期間のうちに成し遂げられたのは、まさに幸運だった。
こうして2006年、OKIワークウェル、オリジナルの多地点音声会議システムが開発されることになったのである。
まずは設計だが、その前に、ネーミングをしなくてはならない。最初のうちは“在宅勤務者向けコミュニケーションシステム”などと呼んでいた。しかし、展示会への出展なども構想する中で、仮称でもいいから製品名を付けようという話になった。
システムの特徴から、おおよそ“~コミュニケータ”になる雰囲気だったが、そこからが、なかなか決まらない。こんな時こそ、アイディアマン・木村の出番である。
「ワークウェルコミュニケータ、でいいんじゃない?」
OKIワークウェルのコミュニケーションツールだから、ということだ。けっこう単純な発想である。
OKIワークウェルという社名も、もともと木村が名付けたものだった。ネットワーカーズの“ワーク”と、ウェルフェアの“ウェル”。その組み合わせで、“うまく働く”という意味を持たせている。
つまり、ワークウェルコミュニケータとは、うまく働くコミュニケーションツール、ということになる。それはシンプルでありながら、なかなか奥の深い命名であった。
次は設計である。ポイントによっては専門家の協力が必要になってくる。設計についても、外部の専門家の手に委ねることにした。VoIP分野を得意とするソフトハウスを探し、その数社に話を持ち込んだ。それぞれに開発の概要を説明し、提案書の作成を依頼。プロの仕事はさすがに速い。提案書は時を待たずして集まった。各々の個性が出ていて、どれも捨てがたいものであった。
総合的に見て、OKIワークウェルの立てた開発方針に、一番釣り合う提案はどれか。その結果、通信系ソフトウェアの開発で成長を続け、また障害者への理解があるマッキーソフト社に発注することになった。
またシステム開発に関する支援をOKIと関連会社が引き受けてくれた。技術コンサルティングには、OKIからは研究開発本部とIPシステムカンパニー(当時)、関連会社からはOKIコンサルティングソリューションズが参加。アクセシビリティに関するコンサルティングには、OKIユビキタスサービスプラットフォームカンパニー(当時)が参加。
さらに、ユーザーインターフェースの仕様設計に関するコンサルティングを、トロント大学でITに関する福祉工学を手がける、マーク・チグネル(Mark Chignell)教授に依頼した。
ワークウェルコミュニケータの開発は、内外の協力によって、順風満帆な船出となったのである。
サクセスストーリー
OKIワークウェルで活躍するOKIネットワーカーズのメンバーを物語でご紹介します。
- いつも前向き
何に対しても一生懸命、P氏。(内部疾患)