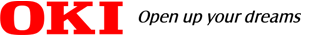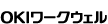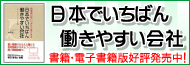- Home
- 職場がおうちへやってきた
- 第7回 - サクセスストーリー
職場がおうちへやってきた
職場がおうちへやってきた 第7回 - サクセスストーリー
[2009年7月16日掲載]
道は開かれる
脊髄性筋萎縮症の中で最も重症といわれる、ウェルドニッヒ・ホフマン病。出生後まもなく発病し急激に進行するため、成人前に亡くなるケースが多い。しかし、OKIネットワーカーズのG氏は、今年で27歳になる。座位が可能で、握力は弱いものの手先は自由に使える。日常生活にも、仕事をするのにも、外出時のほかは車いすが要らない。
Gは理容師の長男として、東京で生まれ育った。物心が付いた時には、すでに歩くことができなかった。しかしその状況は、ごく当たり前のこととして受け入れていた。Gは「大きくなったらお父さんと同じ仕事をするんだ」という夢を描く、純真な子供であった。
それでも、成長する中で、歩ける人たちのことをうらやましく思うようになる。自分の病気がどんなものであるか、それはよく分からなかった。しかし、歩けないということの現実を肌で感じていたのである。
小学校では、身障学級に籍を置き、国語と算数だけ普通学級で受けるという形で過ごした。身障学級では児童2、3人に対して先生が5、6人で、会話も丁寧語が中心だった。そのため、普通学級に行っても同級生との接し方が分からない。Gにも引っ込み思案のところがあったので、クラスメートと今一つ打ち解けることができなかった。
普通学級のクラスメートたちは、子供なりに気を遣っていた。放課後には、いつも何人かが身障学級まで遊びに来てくれた。しかしそれは、障害のあるGを意識しての特別扱いといえないこともない。修学旅行では、どの班がGの面倒をみるかでクラスがもめた。Gはその場にいなかったが、後で知って疎外感を覚えるのだった。
中学では普通学級になった。友達との環境的な隔たりがなくなり、淋しさはなくなった。ところが今度は、身体的な違いが、人間性の違いへとすり替えられていく。そしてGは、いじめを受けるようになった。その上、父親が脳内出血で倒れてしまう。左半身にマヒが残り、理容師の仕事を続けるのが難しくなった。Gは胸を痛めるばかりだった。
中学を卒業すると、バリアフリーの整った都立高校に入学した。介助者を付けることが条件だったが、それはすぐに解決した。Gは父親が倒れて以来、介助サービスを行ういくつかの団体の支援を受けていたのである。
介助者が常にそばにいる、ちょっと窮屈な高校生活。しかし、すぐに友達ができたのと、その友達が介助者の存在を意識せずにいてくれたことが救いとなった。
しかし高3の秋、Gは体調を崩してしまう。長期間のストレスが溢れ出てしまったのだ。不安感や動悸といったものにたびたび襲われ、笑顔も消えた。授業やテスト勉強などにも影響が出た。Gはマイナス思考に傾いていく。大学への進学も断念するのだった。
そんなGの人生に、ある日、思いがけない光が差し込んだ。通っている病院の作業療法士が、社会福祉法人東京コロニーの在宅パソコン講座の存在を教えてくれたのである。Gは小学生の頃からプログラマーに憧れていたのだった。パソコンの話でGと親しくなった作業療法士は、Gの思いを知り、何とか力になれないものかと思っていたに違いない。
〈在宅でなら、やっていけるかも……〉
ただ体力に自信がないがために、控えめになっていたG。しかし、家にいながらパソコン講習を受けられるという話を聞いて、すっかり意欲的になった。
在宅パソコン講座は、苦労もあったが楽しいものだった。何より、いきいきとした毎日を送れるようになった。2年間の講習で、Gはめきめきとパソコン技能の腕を上げていく。そしてGは、自身に秘められた大きな可能性を感じるようになる。
〈社会に出て働きたい……〉
こんな自分であっても、在宅勤務であれば働ける。パソコンの仕事なら自信もある。Gはさらに勉強を続け、基本情報技術者の資格も取得する。
2003年、その努力は大きく花開くことになる。Gは、OKIネットワーカーズとして沖ウィンテック株式会社に採用された。悲願だった就職が実現したのである。最初は、緊張の連続だった。ストレスのために眠れない夜もあった。しかし、障害を意識せずに仕事のできる環境は、Gに、自分らしさを取り戻すチャンスを与えるものだった。
就職から6年。今やGは、その確かな仕事ぶりで信頼され、チームリーダーとしても一目を置かれる技術者の1人となっている。自信と意欲さえあれば、おのずと道は開かれる。Gの生きざまは、それを如実に物語っているのである。
謹厳実直
OKIネットワーカーズ最年長のH氏は、今も脳卒中の後遺症とたたかっている。杖を使えば歩くことができるが、マヒにより、右手はまったく機能しない。また言語障害があり、慌てると単語を忘れてしまうこともある。
そのような状況だが、夫人や成人した息子たちの協力もあって、一日7時間の在宅勤務をこなしている。左手だけでパソコンを操作するので、不自由さは否めない。しかし、とことん筋を通す我慢強さが、Hを支えている。
Hはもともと、OKIの社員だった。大学の工学部を卒業後、1972年にOKIに入社。経営工学を学んだ経験から、管理部や経営情報システム本部に配属された。基幹業務のIT化など、一貫して社内の情報基盤整備に心血を注いだ。スコットランドへ単身赴任し、現地OKIの管理システムを立ち上げた業績もある。
謹厳実直な人柄で知られ、公私にわたって信頼された。縁あって結婚し、2児をもうけた。仕事も家庭も、すべてが順風満帆だった。そんなHに、ある日、病魔が襲いかかる。勤続30年を目前にした、突然の出来事であった。
2002年1月27日、深夜。Hは突然、右の肩に違和感を覚えた。腕もひどく重たい。何が起きたのかも分からないうちに、しびれが全身に広がっていく。
「おい! ……おい! ……おい!」
続けて3回、隣の部屋に寝ていた夫人を呼んだが、それきり声も出せなくなった。精一杯の呻き声を上げると、ようやく夫人が起きてきた。そして、ただならぬ夫の異変に気づくことになる。
命に別条はなかった。意識を失うこともなく、手術も不要だった。それでも後遺症は深刻なものだった。右手足のマヒと言語障害。この時の思いを、Hは「一瞬でドン底につき落とされた感じがした」と述懐している。
数日は絶対安静。その後、2週間の投薬治療を受けた。血圧や脈拍が安定すると、専門施設でリハビリに入った。
幸いなことに、回復にはめざましいものがあった。たった数週間で、Hは自力で立つことができるほどになったのである。言葉も出てくるようになった。左手が右手をフォローする。日常のことが、ほぼ自分でできるようになった。Hは大きな期待に胸を膨らませた。それを後押しするかのように、退院の許可も下りた。
〈この分なら、もうすぐ仕事にだって戻れるだろう〉
Hは退院すると、休職の手続きをとった。そして、すぐさま職場復帰を目指した。自宅で、そして施設で、さらなるリハビリに精を出すのだった。
リハビリに明け暮れる、その生活は2年間にも及んだ。しかし、どんなにがんばっても、それ以上の回復が見られない。右手足のマヒが、一向に良くならないのだ。
〈職場への復帰は、もう無理なのかもしれない……〉
不思議に絶望感はなかった。それより、これからどうするのかが先に立った。長い人生経験から、総合的にものを考える癖が身についているのだ。Hは考えに考えた。この状況下で、自分にできる仕事は何だろう。まったく自由の利かない、こんな自分にでもできる仕事はないものだろうか……。
そんなある日、OKI社会貢献推進室の木村室長が、Hのもとにやってきた。重度障害者を在宅雇用するための特例子会社を作ろうとしている。その新会社に入らないか、という話だった。
木村のことは、よく覚えていた。20年ほど前に、OKIの東京工場で一緒だったことがあるのだ。木村は資材管理課、Hは経営情報本部の東京システム管理課にいた。プライベートでの付き合いはなかったが、仕事の上では、気さくで快活な木村の人柄にほだされるような場面がよくあった。
木村もまた、Hのことを忘れていなかった。脳卒中で倒れたHが、リハビリをがんばっている。それを人づてに聞いて、機会があれば声をかけてみようと思っていたのである。
「あなたなら、だいじょうぶ」
Hは、OKIワークウェルへの入社を決めた。常に身近にあった、ネットワークを使ったパソコン業務。元気な頃には、その存在を特に気に留めてはいなかった。それが今、自分を救おうとしている。
〈新しい人生が始まる……〉
Hは夫人と、久しぶりに湘南の浜辺を歩いた。幼い頃からなじみ親しんだ海だ。広々とした美しい海を見ていると、どこからか力がわいてくる。
「家族が協力してくれるので、助かっています。特に女房には感謝しています」
Hの仕事部屋には、写真とデッサンが飾られている。写真は、息子の高校野球部時代の集合写真。デッサンはHの姉が描いたものである。この仕事部屋で、Hは今日もパソコンに向かっている。
只今、還暦。しかし仕事への意欲は、未だ衰えを見せない。