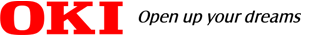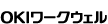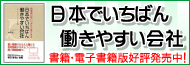- Home
- 職場がおうちへやってきた
- 第6回 - OKIネットワーカーズ誕生秘話
職場がおうちへやってきた
職場がおうちへやってきた 第6回 - OKIネットワーカーズ誕生秘話
[2009年7月1日掲載]
救世主、津田
キオスク端末の画面デザイン。東京コロニーのA青年が期待以上の仕事をしてくれた。ちょっとしたサポートがあれば、たとえ重度の障害を抱えていても、在宅で働くことができるのである。働けるどころか、会社の大きな戦力にも成り得る。木村は重度障害者の在宅雇用を実現させる意義を、改めて確信するのだった。
木村には、もうひとつ大きな目論見があった。1998年7月から、障害者の法定雇用率が従来の1.6%から1.8%にアップする。それに即応するためにも、“在宅勤務による障害者雇用のしくみ”を作る必要があると考えたのである。
障害者を集めて、ただ雇用すればよいという話ではない。障害のある方の経験や感性、技能を充分に活かせるような仕事を用意したい。木村は、ホームページの制作を中心とするクリエイティブな仕事を想定していた。幸いなことに、情報通信を手がけるOKIグループには、在宅勤務に適するソフトウェア関係の仕事がある。ホームページの更新作業なら、どのセクションでも発生する。
問題は、それらの仕事をコンスタントに得られるのか、という点である。仕事が来るときは徹夜になるほど忙しく、来ないときは何ヶ月も閑古鳥が鳴く。そんなことでは企業で働く意味がない。
木村は気づいた。
「複数の在宅勤務者が複数名いれば、多くの職場から、いろんな仕事を恒常的に集められるのではないか……」
木村は、アイディアマンとして知られる。小さなパーツを特徴づけ、それを組み合わせて新しい企画を立ててしまう。そんな木村ならではの発想である。しかし、木村には大きな不安があった。長い間、事務畑を歩いてきたような自分に、そういった仕事の管理ができるのだろうか。次の一手を指せない、木村はそんなもどかしさを覚えるのだった。
ある日のこと。若い男が、木村を訪ねて社会貢献推進室にやってきた。木村は、すぐに彼のことが分かった。
「おお、津田さん! 元気でやっていたか」
「ご無沙汰しています」
津田貴(つだ・たかし)。ソフト開発部門でマネージメントを手がける、OKIの敏腕課長である。慶応義塾大学を出ているので、木村の後輩にあたる。その親しみから、部門を超えてのつながりがあった。
「木村さん、ちょっといいですか」
木村は快くうなずくと、津田をソファーに誘い、自分も向かい側に腰をおろした。
「実は、何か福祉に関わるような仕事ができないかな、と思って伺ったんです」
「それはまた、どうして?」
木村の知る津田は、技術一筋の人間である。そんな彼の口から出た“福祉”という言葉。木村は不思議な感じがした。
「話せば長くなるんですが……」
津田は、これまでの経緯を話し始めた。OKIの球技大会があった。スポーツマンでもある津田は、ソフトボールの試合に出場した。守備はセカンド。ところが、フライを追った瞬間にメンバーとぶつかり、津田は足首の骨を折ってしまった。
ギプスをはめられ、松葉杖での生活を余儀なくされた津田は、それでも会社へ行こうとする。しかし、駅の階段で転びそうになって恐怖を味わう。それ以来、津田は、ほぼ2ヶ月のあいだ、ずっと船橋の自宅で過ごしていた。
思うように身動きがとれない。イライラする。何と不自由なことか。障害を持つ人の気持ちが分かるような気がした。することもなく、テレビや新聞づけになる毎日。つらい思いをしているせいか、暗いニュースにばかり目がいく。事件、事故、自然災害。ひとり暮らしの老人の孤独死に胸が痛む。
ちょうどその頃に、神戸児童殺傷事件が起きた。津田は〈社会がおかしくなってきている〉と感じた。そして、社会のために自分にできることはないか、と考えるようになった。
障害者に関する話題にも、津田は敏感になった。社会を明るくするのに必要なもの……。それは福祉だ。津田は、福祉に関する仕事に携わることを夢に描く。会社を辞めるのもいとわない。大けがが、仕事人間をそこまで変えてしまったのである。
津田の話を、木村はうんうんと聞いていた。津田はメガネを通して、細い目でニコニコしている。しかし、その眼差しはどこか鋭い。
木村はふと、在宅雇用のことを思いつく。彼に、コーディネーターをやってもらうというのはどうだろう。コーディネーターとは、複数のクライアントと在宅勤務者のあいだに立って、仕事をうまくやりくりする役割を担う人間である。プロジェクト・マネージャーでならした津田がそれをやってくれれば、重度障害者の在宅雇用が可能になるのではないか。
「おそらく可能でしょう。お手伝いできると思います」
在宅勤務というものが、日本ではまだ市民権を得ていない当時のことである。津田はなぜ、そんなにあっさりと、在宅雇用に理解を示すことができたのだろうか。それには、大きなベースがあった。
入社12年で課長となった津田は、名古屋にあるOKIの関連会社に出向していたことがある。ソフトウェアの開発を手がける会社だったが、肝心の設計担当者が退職してしまうなど、収拾がつかない状態に陥っていた。だから、気鋭の津田が送り込まれたのかもしれない。
津田はリーダーとして、プロジェクトの立て直しにかかった。巧みな要員計画とスケジューリングが功を奏し、会社の損失は最小限にとどまった。
その中で津田は、その会社におけるプロジェクト運営に、効率の悪さを感じずにはいられなかった。受注は、埼玉県蕨(わらび)市にあるOKIのシステム開発拠点からのものが多かった。そのため、プロジェクトのキーマンは、打ち合わせのために、名古屋と蕨をいちいち行き来しなければならなかったのである。
その頃、北海道や九州の関連会社では、蕨との打ち合わせをテレビ会議で行っていた。津田はそこに目をつけた。テレビ会議を導入すれば、移動時間が節約できて効率が上がる。さらに末端の作業者も、テレビ会議で打ち合わせに参加できれば、効率だけでなくモチベーションも上がる。津田の進言で、会社にテレビ会議システムが導入された。それによって、プロジェクト運営がきわめてスムーズにいくようになった。
この経験から、仕事は離れていても不自由なくできるのだ、という確信を得ていたのだろう。それを瞬時に、在宅勤務に結びつけたのである。
障害者に対しても、津田には純粋な思いがあった。中学から大学まで、津田は卓球の選手として活躍している。OKIに入社してからも、会社のチームに所属し、15年間も試合に出ていたほどである。その中で、障害を持っているのに、津田が勝てないような選手が何人もいた。そんなことから、障害者といっしょに仕事をすることに、まったく違和感がなかったのである。
「分かった。今すぐという訳には行かないが、いっしょにやってくれるか」
「前例のないことですから、なおさら面白そうです。是非やりましょう」
会社の本流でない仕事、それもかなりのリスクがある仕事に臨もうとする。そんな津田の勇気に感服した木村。思いもかけない救世主の登場に、あきらめかけた夢の実現を感じるのだった。
津田が、ソフト開発部門から社会貢献推進室に異動になったのは、それから間もない、1998年4月のことだった。
サクセスストーリー
OKIワークウェルで活躍するOKIネットワーカーズのメンバーを物語でご紹介します。
- 大黒柱として
快活なムードメーカー、E氏。(頚椎損傷) - プラスアルファの挑戦
似顔絵イラストのスペシャリスト、F氏。(筋ジストロフィー)